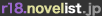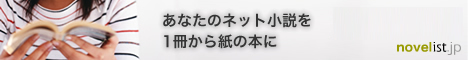未来への警鐘
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和5年4月時点のものです。いつものことですが、似たような事件があっても、それはあくまでも、フィクションでしかありません、ただ、フィクションに対しての意見は、国民の総意に近いと思っています。このお話は、真実っぽい過去の話はあっても、あくまでも、登場する国家、政府、関係者、組織は架空のお話になります。国家や省庁で、どこかで聞いたようなところも出てきますが、あくまでもフィクションです。
帰り道
夜のとばりが下りかけている時間というのは、寂しいという思いが結構感じられるものであった。
時間的には、季節によってハッキリとしないが、湿気を感じる時期というと、寒い時期ではない。
春を通り過ぎ、初夏近くになると、汗が身体に滲んでいるのを感じるのだが、その滲んだ汗が洋服にへばりついてくる気持ち悪さは、
「どんなに冷たくて、身体が凍ってしまったとしても、まだ、冬の方がましなのかも知れない」
と思わせるほどに、気持ちの悪いものだといえるのではないだろうか?
夜のとばりが、普段であれば、まだ、午後7時前くらいまでは明るいと感じるのに、その日はすでに、6時まえくらいから、
「まもなく真っ暗になるだろうな」
ということを予感させるものだった。
春から夏にかけてというと、実はあまり好きな季節ではない。
「春が心地よい」
と思うのは、世間では言われている、いわゆる、
「ゴールデンウイーク」
と呼ばれる時期までだろう。
桜が咲く頃までは、まだまだ寒さが残っていて、年によっては、
「肌寒さ」
が感じられ、花見の時など、底冷えがしてくると、トイレが我慢できなくなる。
男性の場合は、そこまで気にするほどではないのだが、これが女性とのなると、そうもいかなくなるのであった。
というのは、
「男性のように、簡単にはいかない」
ということであり、一度我慢してしまうと、女性の身体は、そんなに簡単に元に戻れないということもあり、問題となるといっても過言ではない。
「それが分かっているのに、どうして、花見なんて風習はなくならないんだ?」
と思っている人も多いだろう。
下手をすれば、膀胱炎を通り越して、
「救急車で運ばれる人が後を絶えない」
ということも少なくないだろう。
そんなことを考えていると、
「自業自得」
といえばそれまでなのだが、それでは片付けられない。
「行政は一体どうするんだ?」
ということである。
何と言っても、まだ肌寒い時期に、酒を飲むわけである。途中で、
「トイレに行きたい」
と思っても、楽しさからか、我慢してしまうのも、無理もない。
しかし、我慢できなくなってトイレに行っても、そこにあるのは、長蛇の列。
「しまった」
と思っても、後の祭りである。
「そんなことは分かっていたはずだ」
という人は、本当にそうなのだろうか?
「トイレにまでくれば何とかなる」
と思っていた人は、ここで、まず、大いなるショックを受けてしまうのだ。
果てしない絶望感とともに、一緒に、後悔が走るのだろうか?
もうそんな余裕などないに違いないが、きっと後悔をするのだと思う。後悔をしないと、自分を許せないまま、気絶してしまい、
「その後ろめたさからか、下手をすれば、目を覚ますことができなくなるのではないだろうか?」
と考えてしまうのではないかと思うのだった。
そして、その時のことが大いなるショックで、何か後遺症のようなものが残ってしまいかねないと考えられる。
その時、車を走らせて、帰宅の途に就いていた豊島治子だったが、彼女も、数年前の忘年会で、同じ目に遭ってしまい、それから、軽い健忘症のようになってしまい、
「短い期間、ふと記憶が消えてしまう」
ということがあったり、
「何かを思い出そうとしたのだが、次の瞬間、何を思い出そうとしたかということを、思い出せない」
というようなことになっていたりするのだった。
それが、その時の後遺症であり、トラウマ、いや、
「PTSDのようなものだ」
ということを自覚しているのであった。
「トラウマが残ってしまったことで、何らかのショッキングなことが起こると、フラッシュバックしてくるのか、その時によって、いろいろな状況に陥ってしまうのではないか?」
と感じるのだった。
トラウマというのが、
「何かショックなことがあった時の時だけを思い出すのだ」
というわけではなく、他の要因で引っかかっていることがあったとしても、それが、似たような症状を引き起こすという意味で
「自分が一体、どう感じればいいのか?」
ということを感じるようになったのだろう。
豊島治子がその時間の帰宅というのは、珍しいことではない。
なぜなら、仕事を普通に終えて会社を普通に出れば、家の近くに来るのが、ちょうど今くらいの時間だったからだ。
会社の勤務時間が、午後六時まで、そして、服を着かえたり、駅に行き、電車に乗って、最寄りの駅まで来て、そこから徒歩で家まで帰る。
たまに家の近くのスーパーか、コンビニに寄るのだが、その日は、別に寄り道をする予定もなかったので、ほぼ午後七時前に、このあたりを通過することになる。
この時間というと、まだまだ通勤時間で、帰宅の途に就いている人も結構いる。その証拠に電車では、いつも座ることもできず。駅を降りると、お約束の、改札までの人の波であった。
それに巻き込まれないようにするには、最初から、階段の目の前の乗降口で、到着後、一気に飛び出すという、
「臨戦態勢」
でもって望むか。
あるいは、階段から一番遠く、たとえば、電車の一番前か、後ろの車両に乗り込み、わざと最後にゆっくりと降りて、人込みを避けるように、階段では、ゆっくりと改札に向かおうとするような消極的な降り方をするかということである。
学生時代の頃までであれば、
「臨戦態勢」
というのもやむなしであった。
しかし、社会人になって、まわりの目が気になるようになってくると、そんなに一気に、目立つようなことはしなくなったのだ。
しかも、数年前に、伝染病が流行ったことで、マスク生活を余儀なくされたことからか、基本的に、人込みに差し掛かることを避けるようになっていたのだ。
これは、治子だけに言えることではなく、他の人にも言えることなのか、全体的に動きがゆっくりになってきたのだ。
帰り道
夜のとばりが下りかけている時間というのは、寂しいという思いが結構感じられるものであった。
時間的には、季節によってハッキリとしないが、湿気を感じる時期というと、寒い時期ではない。
春を通り過ぎ、初夏近くになると、汗が身体に滲んでいるのを感じるのだが、その滲んだ汗が洋服にへばりついてくる気持ち悪さは、
「どんなに冷たくて、身体が凍ってしまったとしても、まだ、冬の方がましなのかも知れない」
と思わせるほどに、気持ちの悪いものだといえるのではないだろうか?
夜のとばりが、普段であれば、まだ、午後7時前くらいまでは明るいと感じるのに、その日はすでに、6時まえくらいから、
「まもなく真っ暗になるだろうな」
ということを予感させるものだった。
春から夏にかけてというと、実はあまり好きな季節ではない。
「春が心地よい」
と思うのは、世間では言われている、いわゆる、
「ゴールデンウイーク」
と呼ばれる時期までだろう。
桜が咲く頃までは、まだまだ寒さが残っていて、年によっては、
「肌寒さ」
が感じられ、花見の時など、底冷えがしてくると、トイレが我慢できなくなる。
男性の場合は、そこまで気にするほどではないのだが、これが女性とのなると、そうもいかなくなるのであった。
というのは、
「男性のように、簡単にはいかない」
ということであり、一度我慢してしまうと、女性の身体は、そんなに簡単に元に戻れないということもあり、問題となるといっても過言ではない。
「それが分かっているのに、どうして、花見なんて風習はなくならないんだ?」
と思っている人も多いだろう。
下手をすれば、膀胱炎を通り越して、
「救急車で運ばれる人が後を絶えない」
ということも少なくないだろう。
そんなことを考えていると、
「自業自得」
といえばそれまでなのだが、それでは片付けられない。
「行政は一体どうするんだ?」
ということである。
何と言っても、まだ肌寒い時期に、酒を飲むわけである。途中で、
「トイレに行きたい」
と思っても、楽しさからか、我慢してしまうのも、無理もない。
しかし、我慢できなくなってトイレに行っても、そこにあるのは、長蛇の列。
「しまった」
と思っても、後の祭りである。
「そんなことは分かっていたはずだ」
という人は、本当にそうなのだろうか?
「トイレにまでくれば何とかなる」
と思っていた人は、ここで、まず、大いなるショックを受けてしまうのだ。
果てしない絶望感とともに、一緒に、後悔が走るのだろうか?
もうそんな余裕などないに違いないが、きっと後悔をするのだと思う。後悔をしないと、自分を許せないまま、気絶してしまい、
「その後ろめたさからか、下手をすれば、目を覚ますことができなくなるのではないだろうか?」
と考えてしまうのではないかと思うのだった。
そして、その時のことが大いなるショックで、何か後遺症のようなものが残ってしまいかねないと考えられる。
その時、車を走らせて、帰宅の途に就いていた豊島治子だったが、彼女も、数年前の忘年会で、同じ目に遭ってしまい、それから、軽い健忘症のようになってしまい、
「短い期間、ふと記憶が消えてしまう」
ということがあったり、
「何かを思い出そうとしたのだが、次の瞬間、何を思い出そうとしたかということを、思い出せない」
というようなことになっていたりするのだった。
それが、その時の後遺症であり、トラウマ、いや、
「PTSDのようなものだ」
ということを自覚しているのであった。
「トラウマが残ってしまったことで、何らかのショッキングなことが起こると、フラッシュバックしてくるのか、その時によって、いろいろな状況に陥ってしまうのではないか?」
と感じるのだった。
トラウマというのが、
「何かショックなことがあった時の時だけを思い出すのだ」
というわけではなく、他の要因で引っかかっていることがあったとしても、それが、似たような症状を引き起こすという意味で
「自分が一体、どう感じればいいのか?」
ということを感じるようになったのだろう。
豊島治子がその時間の帰宅というのは、珍しいことではない。
なぜなら、仕事を普通に終えて会社を普通に出れば、家の近くに来るのが、ちょうど今くらいの時間だったからだ。
会社の勤務時間が、午後六時まで、そして、服を着かえたり、駅に行き、電車に乗って、最寄りの駅まで来て、そこから徒歩で家まで帰る。
たまに家の近くのスーパーか、コンビニに寄るのだが、その日は、別に寄り道をする予定もなかったので、ほぼ午後七時前に、このあたりを通過することになる。
この時間というと、まだまだ通勤時間で、帰宅の途に就いている人も結構いる。その証拠に電車では、いつも座ることもできず。駅を降りると、お約束の、改札までの人の波であった。
それに巻き込まれないようにするには、最初から、階段の目の前の乗降口で、到着後、一気に飛び出すという、
「臨戦態勢」
でもって望むか。
あるいは、階段から一番遠く、たとえば、電車の一番前か、後ろの車両に乗り込み、わざと最後にゆっくりと降りて、人込みを避けるように、階段では、ゆっくりと改札に向かおうとするような消極的な降り方をするかということである。
学生時代の頃までであれば、
「臨戦態勢」
というのもやむなしであった。
しかし、社会人になって、まわりの目が気になるようになってくると、そんなに一気に、目立つようなことはしなくなったのだ。
しかも、数年前に、伝染病が流行ったことで、マスク生活を余儀なくされたことからか、基本的に、人込みに差し掛かることを避けるようになっていたのだ。
これは、治子だけに言えることではなく、他の人にも言えることなのか、全体的に動きがゆっくりになってきたのだ。